#地域#環境
原子力事故被害者への完全賠償と
損害賠償制度とは。
久保 壽彦佛教大学 社会学部教授
Introduction
2011年3月の東京電力福島第一原子力発電所の事故後、10兆円を超える巨額の損害賠償請求が東京電力になされている。久保壽彦教授は、被害者を守りつつ、原子力事業者の倒産を防ぐ原子力損害賠償制度のあり方を検討している。
東京電力福島原発事故後の損害賠償制度を考える
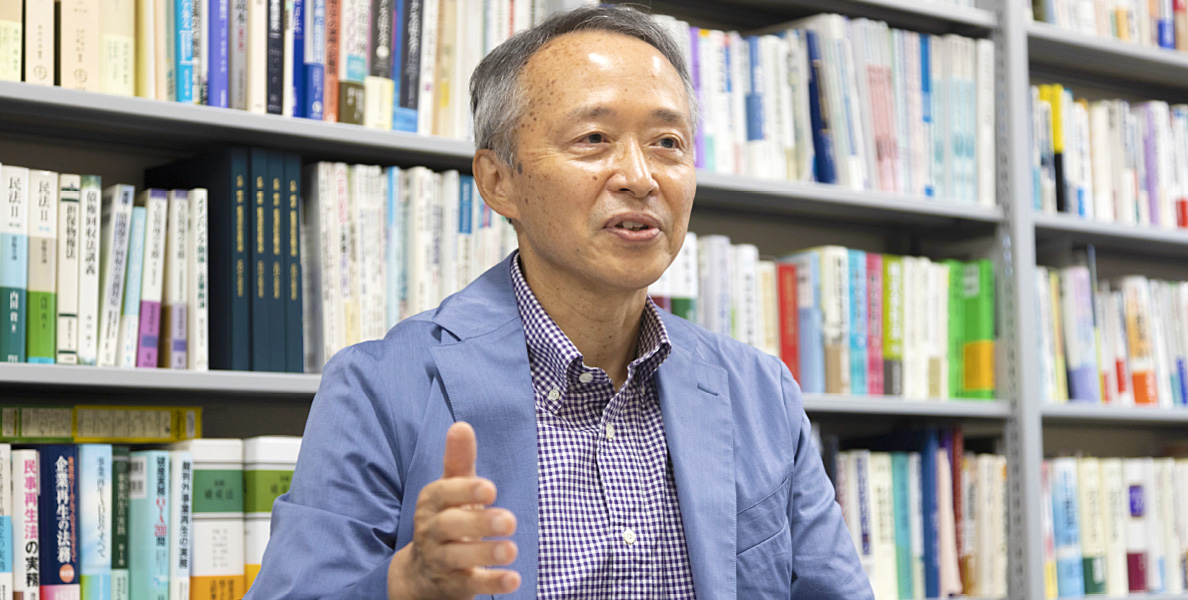
2011年3月11日の東日本大震災によって引き起こされた東京電力福島第一原子力発電所(以下、東電福島原発)事故は、地域に未曾有の被害をもたらした。原子力発電所の周囲は数十kmにわたって避難指示区域に指定され、一時避難や転居を余儀なくされた人をはじめ、さまざまな被害を受けた人は膨大な数にのぼる。それに対し、これまでに東京電力が支払った損害賠償金額は10兆円を超えた。それに加えて廃炉や除染などにかかる諸費用を合わせると、15兆円を超える金額になると試算されている。
「これほど巨額の賠償を負ってなお事業を継続できる企業は、わが国最大の電力会社である東京電力ほか大規模な原子力事業者のみです。もし地方の原子力事業者が同じ規模の事故を発災させたら、一体どうなるのか」という問題意識から、久保壽彦教授は東電福島原発事故に伴う損害賠償制度について検討し、より良い方策を模索してきた。
巨額の原子力損害賠償を支援する仕組み
「現行の『原子力損害の賠償に関する法律』(以下『原賠法』)では、原子力損害について、原子力事業者に無過失責任・責任集中・無限責任が課せられており、ひとたび事故が起きた際には、原子力事業者が全責任を負うよう定められています。これが免責されるのは、『異常に巨大な天災地変又は社会的動乱』が起こった時だけに限定されています」。久保教授の解説によると、原賠法では、迅速かつ適切な被害者保護を図るため、一つの発電所あたり1200億円の損害賠償措置を講ずることが原子力事業者に義務付けられている。ただし、もしこれを超える原子力損害が生じた場合は、国が援助することも定められているという。福島原発事故後、当初は原賠法第3条の免責規定に該当するかどうかが問題となったものの、東京電力は賠償責任を果たす意思を示し、「国の援助」を要請した。その結果、政府補償契約に基づき、2011(平成23)年8月3日には新法「原子力損害賠償支援機構法」、現在の「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(以下「支援機構法」)が成立する。「この法律によって、国の原子力事業者への資金援助が具体化されました。一方で、9つの原子力事業者が相互に支え合う相互扶助ルールに基づいて援助を受ける原子力事業者以外の原子力事業者も、援助に必要な資金を負担する義務を負うこととされました。これにより、東京電力は特別負担金を支援機構に支払い、その他の原子力事業者が一般負担金をプールする仕組みができました」と言う。国は資金援助の原資として、これまでに総額10兆円の国債を支援機構に交付し、支援機構はそれで得た資金を東電に資金援助し、賠償に充てている。
保険的なスキームで原子力事業者の破綻を防ぐ
「原発事故に伴う賠償や廃炉費用の推計は増大しており、もし東京電力と同程度の損害賠償債務を地方の原子力事業者が負担すると仮定した場合、300年を超えても支援機構への返済が終わらないと想定されます」と久保教授。そうなれば久保教授が懸念した通り、事故を起こした原子力事業者は債務超過的財務状況に陥り、加えて電気事業法の改正によって会社更生手続や破産手続などの法的整理を行う可能性も出てくる。「しかし原子力事業者が倒産してしまったら、被害者への賠償がままならなくなるばかりか、電力の安定供給も危うくなるかもしれません。地域経済に与える影響も計り知れません」と指摘する久保教授は、倒産手続きなどの法的整理はできるだけ慎重になるべきだという立場から、原子力事業者の経営規模に応じたきめ細かな損害賠償制度を再構築することを提言する。
「原発を保有する電力会社9社を企業規模によって三つのグループに分けようというものです。具体的には、大都市中心の大規模事業者グループと、地方中核都市中心の中規模事業者グループ、そして地方都市の事業者グループに区分し、それぞれについて損害賠償制度を見直すべきだと考えています」と語る。具体的には、大都市事業者グループについては現行制度を維持し、地方中核都市事業者グループに関しては、事業者間の保険制度的な枠組みを構築することで、賠償資金を担保するという。また地方都市事業者グループについては、債務超過的財務状況によって企業の存続が極めて難しくなるとして、可能な限り法的整理を避けつつも、それを視野に入れた新たな損害賠償制度の枠組みを検討していく必要があるとした。

保険制度的な枠組みとは、相互扶助ルールを拡張し、現在支援機構に支払われている一般負担金を、電力利用者から徴収する一種の「保険料」とみなし、賠償責任保険的な仕組みとして再制度化を図ろうというものだ。実質的には金融機関の預金保険制度と似た保険制度が想定され、加えて特別法(例えば、金融機関に関する会社更生の特例に関する法律)のような手続をバックアップする特別法)を制定するべきであるという。
久保教授は、30年生命保険会社に勤務し、資産運用や企業法務に携わった後、研究者に転じた。そのキャリアから、民事法や会社法を専門として判例分析を行うだけでなく、それが金融実務や実社会にどのような影響を及ぼすのかに着眼点を置く。原子力損害賠償法についても決してその視点を失わず、実社会への貢献を見据え、研究を続けている。
BOOK/DVD
このテーマに興味を持った方へ、
関連する書籍・DVDを紹介します。
-

『金融機関の法務対策6000講』金融財政事情研究会
-

『原子力損害賠償法』野村豊弘/第一法規
-

『法の世界へ(第9版)』池田真朗/有斐閣
-

『安全保障戦略』兼原信克/日本経済新聞社
教員著作紹介
-
「金融取引法の課題」『立命館経済学』立命館大学経済学会
-
「東日本大震災被災地における二重債務問題と金融機関の経営問題」立命館大学経済学会
-
「原子力損害賠償制度の課題」『立命館経済学』立命館大学経済学会
-
「保険会社による債権回収と保険法改正」『事業再生と債権管理』金融財政事情研究会
-
『ケースでわかる破産法』金融財政事情研究会
久保 壽彦/ 佛教大学 社会学部教授
KUBO Toshihiko

