#地域#国際#日本
未曾有の人口減少を乗り越える
一手とは?
政府の単位を超えた連携を考える。
原田 徹佛教大学 社会学部准教授
Introduction
人口減少が進展する中、行政サービスの維持が困難になる地域が出てくることが危惧されている。EU・ヨーロッパの政治と公共政策を研究する原田 徹准教授は、その打開策として、日本においても政府の単位を超えた連携に注目する。
未曾有の人口減少が
地域社会に大きな影響を及ぼす

日本の人口は、2008(平成20)年に1億2,808万人でピークに達して以降減少に転じ、2022(令和4)年には1億2,500万人を割り込んだ。今後も急勾配に減少し続け、2100年には、4,950万人になるという予測さえある。
人口減少は、我々が暮らす社会にさまざまな影響を及ぼす。「地域経営の観点では、住民税が減り、行政サービスの維持が難しくなることが危惧されます。税収減少はこれに留まりません。国から自治体への財政移転の仕組みである地方交付税は、住民人口が算定基準に設定されているため、人口減少が著しい自治体は国からの交付額が減り、地方財政がひっ迫することになります。それによって、例えば、インフラの整備・補修が後回しにされるなど、住民の暮らしのあらゆる方面に問題が波及していくと考えられます」
そう説明した原田 徹准教授は、これまで特にEU・ヨーロッパの政治と公共政策に焦点を当てて研究してきた。EUに代表されるように、国や自治体といった政府の単位を超えた政治や政策に関心を持っている。
自治体の機能を補完し合う
多様な「連携」のかたち
「日本においても、人口減少がもはや避けられない既定路線と受け止められる中、人口減少によって行政サービスの持続が困難になった自治体の機能を補うため、近隣の地方政府同士が連携したり、上層の政府と下層の政府が関係を見直し、複数の政府間の役割分担を再編することで問題解決を図ろうとする動きが出てきています」として原田准教授は、「タテ」と「ヨコ」の二つの政府体系のモデルを提示した。
一つが「垂直的な政府体系モデル」である。この中には、上層の政府と下層の政府、国と自治体の役割分担をはっきり分け、権限区分を明確にする「制限列挙モデル」別名「レイヤーケーキ・モデル」と、自治体に包括的な権限が与えられ、それに重複するかたちで国が関わり、国と自治体の役割分担があいまいな「包括授権モデル」すなわち「マーブルケーキ・モデル」がある。原田准教授によると、2000年以降の地方分権改革の中で、二重行政のデメリットが指摘され、「レイヤーケーキ・モデル」の効率性・合理性が支持されてきたが、時には権限が重複していることが利点になることもあるという。「2011年の東日本大震災後、東北の自治体が機能不全に陥る中で、国の出先機関である国土交通省東北整備局がバックアップ機能を発揮したことがありました」
こうした「タテ」の連携に対し、原田准教授がより注目するのが、「ヨコ」のつながりを重視する「水平的な政府体系モデル」である。2010年に発足した関西広域連合のように、複数の都道府県が事務を共同処理する制度もその一つだ。東日本大震災後、関西広域連合が主導し、被災自治体と支援する府県をペアにする「対口支援」方式で、関西地域に避難してきた被災者を各府県に円滑に受け入れたことは、ヨコ連携の成功例といえる。
「2000年代に入り、市町村合併のように、法制度によって、都道府県という上層の政府が、下層の市町村を助ける、言ってみれば『連携』というより『統合』のかたちが見られるようになりました」と原田准教授。同じ層に位置する政府間での連携でも、持続困難になった行政サービスを補完し合う「相互連携」だけでなく、「相互競争」モデルを適用した人口減少対策も多く実践されてきたという。「しかしある自治体が行政サービスを充実させ、近隣地域の住民を呼び込むことで人口増加を図っても、パイが変わらなければ、単に人口移動が起こるだけで、根本的な解決策にはなりません」と原田准教授は疑義を唱える。
とはいえ「『相互連携』モデルも完璧ではない」と言う。「例えば、2014年に導入された連携中枢都市圏という仕組みがあります。これは、地域の中心都市(三大都市圏外の人口20万人以上の政令指定都市と中核市)が、近隣の周辺市町村と連携することで、圏域全体で必要な生活機能などを確保し、人口と社会経済の活力を維持しようという試みです」。導入後、連携数は増えているが、同時に問題も指摘されている。国の財政措置の恩恵を手厚く受けられる中心市が周辺の市町村の囲い込みに躍起になり、中心市間で市町村を奪い合うという、先述の「相互競争」モデルと同じような事態が起こっているというのだ。
では人口減少に伴う問題に善処していくために地方政府はどうするべきなのか。「国に提示された事業を機械的に受容するのではなく、冷静に検討し、戦略的・能動的に取捨選択していく態度が求められます」と答えた原田准教授。各自治体が複眼的な視野を持ちながら、自らの地域社会にふさわしい公共政策をデザインし、実行する能力を持つ必要性を説いた。

得か損か。
政治・政策を動かす思惑への
憤りが研究の原点
「政府が政治の単位を変えようとする背景には、必ず経済的な思惑が働いています。得か損かで事態が動き、いつの間にか本来の目的を消し去ってしまうことに疑念や憤りを感じます」。原田准教授は、研究を続ける原動力をこう語る。
長く研究を続けているEUについても同様の問題意識を持っている。「もともとは第二次世界大戦後、二度と戦争を繰り返さないために統合を目指したのが出発点でした。ところが経済統合の中で、いつしか『平和実現』という本来の目的は後景に退き、経済的に利があるか否かが、政策決定・実行の原理になってしまっています」と言う。
近年、新型コロナウイルスの感染拡大、ウクライナ紛争など、ヨーロッパはもとより世界中に甚大な影響を及ぼす問題に直面する最中、EUの連携はどうなっていくのか。今後も注視していく。
BOOK/DVD
このテーマに興味を持った方へ、
関連する書籍・DVDを紹介します。
-
『月刊 ガバナンス』ぎょうせい
-
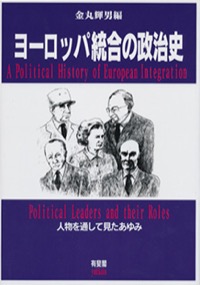
『ヨーロッパ統合の政治史』金丸輝男 編/有斐閣
-
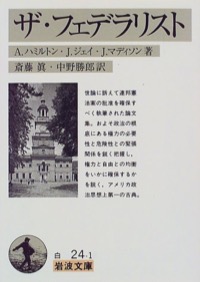
『ザ・フェデラリスト』A. ハミルトン、J. ジェイ、J. マディソン(斎藤眞・中野勝郎 訳)/岩波書店
-

『公共の哲学』片岡寛光/早稲田大学出版部
-
『縮小ニッポンの衝撃』NHKスペシャル取材班/講談社現代新書
-
『リベラルとは何か』田中拓道/中公新書
教員著作紹介
-
『人口減少社会の地域経営政策』
晃洋書房(共著) -
『国際機構〔新版〕』
岩波書店(共著) -
『トランスナショナル・ガバナンス』
岩波書店(分担翻訳) -
『国境の思想』
岩波書店(共訳) -
『EUにおける政策過程と行政官僚制』
晃洋書房
表彰
-
日本公共政策学会 2019年度学会賞(奨励賞)
原田 徹/ 佛教大学 社会学部准教授
HARADA Toru
[職歴]
- 2016年4月~2019年3月同志社大学・政策学部・助教
- 2019年4月~2023年3月佛教大学・社会学部公共政策学科・講師
- 2023年4月~現在に至る 佛教大学・社会学部・准教授


