#仏教#地域#こころ
お寺の社会活動が示す
「ともに生きる仏教」の可能性
大谷 栄一佛教大学 社会学部教授
Introduction
被災地支援や子育て支援などさまざまな社会活動を行うお寺が増えている。大谷栄一教授は、近現代仏教の歴史をひも解きつつ、「仏教の社会活動」の意義と可能性を論じる。
若い僧侶たちによる「仏教の社会活動」が増えている

日本にはコンビニエンスストアをはるかに凌ぐ数の寺院がある。しかし多くの人にとってその存在は、身近なものとはいえない。かつてはどの地域にも当たり前にあった寺と檀家の関わり(寺檀制度)が衰退していく中で、日本の仏教は次第にその存在感を失ってきた。そんな仏教界に2000年以降、若い世代の僧侶たちによる「仏教の社会活動」という新たな波が到来しているという。なぜ、お寺が社会活動をするのか? 大谷栄一教授は、近現代仏教の歴史をひも解きながら、その問いに答えている。
近現代仏教に着目する理由を大谷教授はこう語る。「従来の日本仏教の研究は鎌倉時代に焦点が当てられており、明治維新から第二次世界大戦を経て今にいたる近代、現代の仏教についてはあまり議論されてきませんでした。しかし現代仏教の原型の多くは、近世から近代に形づくられたものであり、『今の仏教』を考える上で、近現代仏教への視点を欠くことはできません」。例えば現代の仏教は、葬式や先祖の供養をするだけだとの非難の意を込めて「葬式仏教」といわれるが、その起源は近世(江戸時代)にまで遡る。大谷教授によると、この頃に多くの民間寺院が設立され、寺檀制度や本末制度、先祖祭祀、戒名・位牌・仏壇・墓石といった「葬式仏教」につながる制度や慣わしが定着したのだ。
明治時代から仏教は公共的な役割を担ってきた
「仏教の社会活動」もまた、こうした仏教の歴史的変遷の中に位置づけることができると大谷教授は語る。教授によると、仏教者や仏教団体による社会活動は、古代や中世にすでに見られたが、近代に大きく発展したという。「明治から昭和前期までは、仏教者が医療救護の面で大きな役割を果たしてきました。また社会福祉制度が未熟だった戦前に国の福祉政策を補完したのは、他でもなく仏教界でした」。つまり近代の仏教界は、公共的な機能の担い手として大きな存在感を持っていたのだ。
 滋賀教区浄土宗青年会のおうみ米一升運動。東日本大震災の被災地での近江米配布会の様子(平成26年11月撮影)。写真提供:曽田俊弘師(浄土宗滋賀教区)。
滋賀教区浄土宗青年会のおうみ米一升運動。東日本大震災の被災地での近江米配布会の様子(平成26年11月撮影)。写真提供:曽田俊弘師(浄土宗滋賀教区)。
戦後、福祉国家体制の整備や政教分離の原則などによって、公共的機能を担った仏教は存在感を失っていく。「それが2000年代以降、アカデミズムやマスメディアで宗教の公共性や公益性が議論されるようになるのと連動して、再びお寺による社会活動が活性化してきました」と大谷教授。その背景のひとつとして、1995年のオウム真理教による地下鉄サリン事件があると見る。事件をきっかけに、宗教団体のあり方が問い直されるようになったことは、多くの人の知るところだ。加えて「1995年の阪神・淡路大震災で多くの宗教者や宗教団体が被災地支援に関わった経験から、社会により積極的に関わる機運が醸成されたことも理由と考えられます」と分析する。さらに2011年、東日本大震災後、多くの仏教者・寺院が支援や復興活動に尽力したことで、「仏教の公共性」が世間の耳目を集めるようになった。また、弔いや死者供養という仏教の力も再評価された。
「ともに生きる仏教」が地域社会をつくる
それにしても個人や団体を問わず、多様な社会活動が行われている中にあって、仏教者や寺院の社会活動にはどのような意味があるのだろうか。
大谷教授は、「仏教の社会活動」を「仏教者、仏教団体、寺院が仏教の教え・思想や信仰に基づき、社会問題の解決や人々の生活の質の維持・向上を図る活動」と定義する。教授によると、大乗仏教の系譜を引き、自らの悟りを追求しつつ(自利)、他者の救済(利他)を行うことが重視される日本の仏教では、「宗教活動」「教化活動」、そして「社会活動」が行われており、他者を救うための修行(菩薩行)の一環として社会活動がある。「『自らが仏になるとともにすべての人々の救済をする』という仏教の教えに根差している」という点で、「仏教の社会活動」と「世俗的な社会活動」には決定的な違いがあるのだ。
現代、仏教者や寺院による社会活動は、サービス系(社会福祉、ボランティア、人道支援、イベントなど)やアクティビズム系(政治活動、社会活動、平和活動)など多岐にわたる。とりわけ大谷教授は、「発心」を持ち、多様化する現代の社会課題の解決の一助となるべく精力を傾けている宗教者や寺院に共鳴し、その活動や意義を広く社会に発信することにも力を注いでいる。2006年から5年間、「宗教と社会」学会のプロジェクトとして、「宗教の社会貢献活動研究プロジェクト」を研究者仲間とともに推進。宗教の社会的な役割や社会活動の成果を確認し、宗教の公共的役割の重要性を浮き彫りにした。
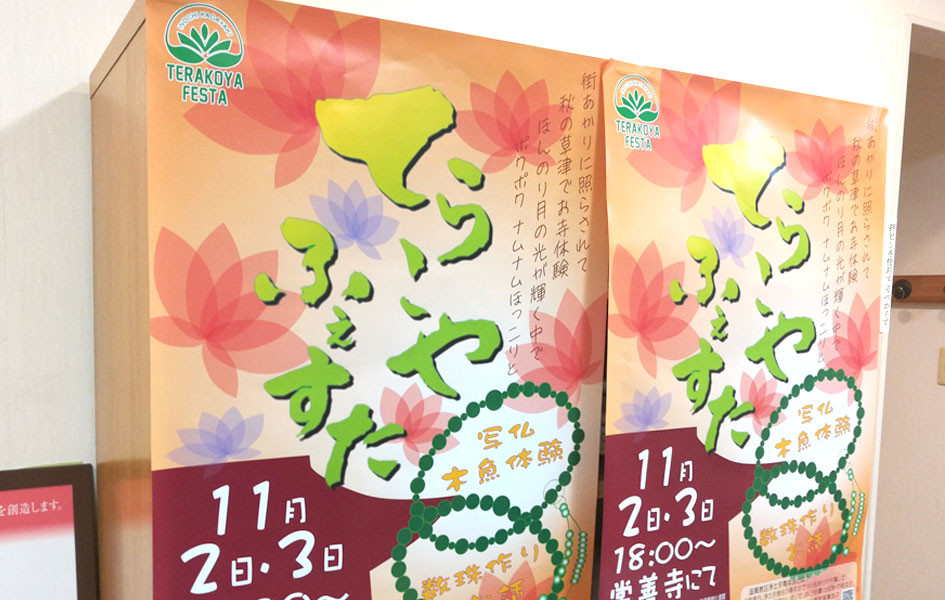 滋賀教区浄土宗青年会のてらこやフェスタのポスター(平成29年11月撮影)
滋賀教区浄土宗青年会のてらこやフェスタのポスター(平成29年11月撮影)
「日本の仏教が『地域に開き』、ソーシャル・キャピタル(社会関係資本)の源泉として機能することで、現代においてもより明確な存在意義を示せる」と指摘する大谷教授。これまで日本の寺院は、寺檀制度に立脚し、内部の人々とのつながりを強める結合型のソーシャル・キャピタルとして機能してきた面が強かった。「しかし現代では、今まで以上に社会に開き、外部とのつながりや情報の流通に優れた潤滑油の役割を果たす橋渡し型のソーシャル・キャピタルも醸成する必要がある」として、社会活動を通じて地域のさまざまな立場の人々と「ともにする」ことの重要性を説く。それに加えて重視するのが、「ともにある」という姿勢だ。2011年の東日本大震災後、仏教者が医療や福祉関係者と協働で行ったのが、「心のケア」という支援だった。東北大学をはじめいくつもの大学でこうした「心のケア」を担う臨床宗教師の養成が始まったことも顕著な例だ。布教や伝道のみならず、苦悩や悲嘆を抱える人の想いにただ寄り添い、「ともにある」ことにも目を向ける。
「お寺を開き、『ともにする』『ともにある』を実践する。そんな『ともに生きる仏教』が、地域社会の結節点としての機能を果たし、『地域社会をつくる』役割を果たせるのではないか」と大谷教授。「さまざまな問題を抱える現代社会で、仏教にできることはもっとあるはずです。社会により積極的に関わるこれからの仏教に期待したい」と結んだ。
BOOK/DVD
このテーマに興味を持った方へ、
関連する書籍・DVDを紹介します。
-

『近現代仏教の歴史』吉田久一/筑摩書房
-
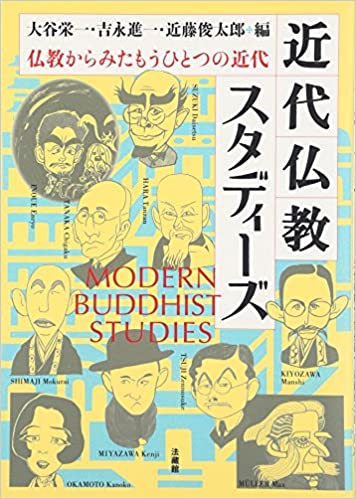
『近代仏教スタディーズ』大谷栄一他編著/法蔵館
-
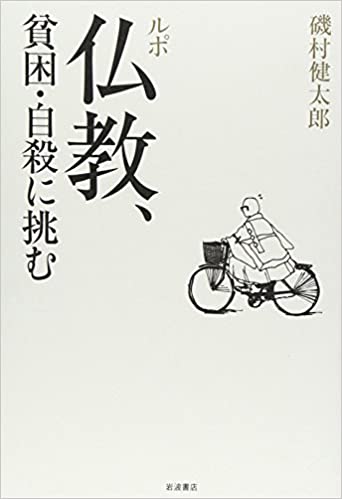
『ルポ仏教、貧困・自殺に挑む』磯村健太郎/岩波書店
-
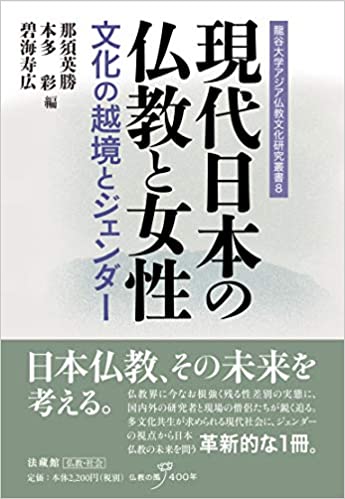
『現代日本の仏教と女性』那須英勝他編/法藏館
-
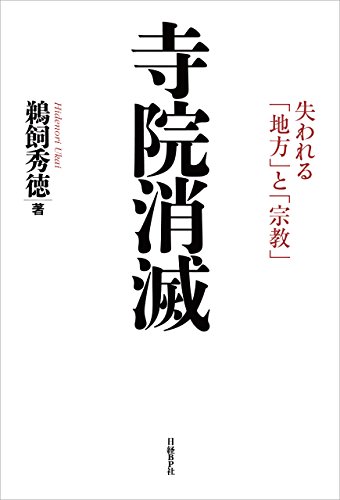
『寺院消滅』鵜飼秀徳/日経BP社
-
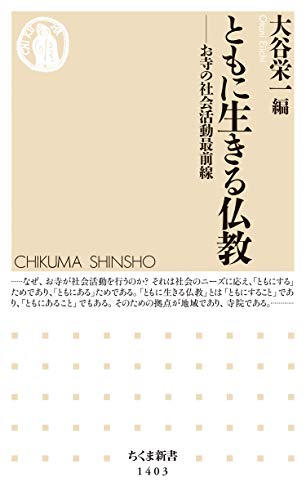
『ともに生きる仏教』大谷栄一編著/筑摩書房
教員著作紹介
-
『地域社会をつくる宗教』共編者/明石書店
-
『人口減少社会と寺院―ソーシャル・キャピタルの視座から』分担執筆/法藏館
-
『日蓮主義とはなんだったのか─近代日本の思想水脈』講談社
-
『近代仏教というメディア─出版と社会活動』ぺりかん社
-
『近代日本宗教史』全6巻共編著/春秋社
大谷 栄一/ 佛教大学 社会学部教授
OTANI Eiichi
[職歴]
- 1999年4月~2005年3月 (公財)国際宗教研究所 研究員
- 2005年4月~2009年3月 南山宗教文化研究所 研究員
- 2009年4月~2016年3月 佛教大学社会学部 准教授
- 2016年4月~現在に至る 佛教大学社会学部 教授


