#子ども#ケア#家族#障害#こころ
精神疾患のある親をもつ子どもを支える。
田野中 恭子佛教大学 保健医療技術学部准教授
Introduction
精神疾患のある親をもつ子どもの困難について、日本ではまだあまり認識されていない。田野中 恭子准教授は、研究や取り組みが進むドイツの事例をもとに、子どもへの支援の必要性を説く。
親がこころの病気になった子どもを描いた児童書が反響

親がこころの病気になった子どもを主人公にしたドイツの児童書『悲しいけど、青空の日』(サウザンブックス、2020)が邦訳され、2020年6月、出版された。
本書は3部構成で、第1章は9歳の少女モナの物語が描かれる。こころの病気を抱えるママと2人暮らしのモナがどんなことを困難に感じ、どんな思いを抱いているのか。モナを通じて親がうつ病などのこころの病気になった子どもの実情や気持ち、必要な支援が語られる。タイトルは、誰にも相談できずにいたモナが、勇気を出して学校の先生にママのことを話した時、先生がかけてくれた言葉にちなむ。「ママの調子が悪くなるのは、あなたのせいではないのよ。あなたはみんなと同じように楽しくしていていいのよ。そうしたら、『悲しい日』を『悲しいけど、青空の日』にすることができるでしょう?」と。
本書は物語だけで終わらず、第2章で子どもにも理解しやすい言葉でこころの病気について解説され、さらに第3章では、大人向けの解説とともに支援機関の連絡先も掲載される。
翻訳を手がけたのは、精神疾患のある親をもつ子どもについて研究する田野中 恭子准教授だ。クラウドファンディングで資金を集め、出版にこぎつけた。「日本では、これまで精神疾患を患う当事者や周囲の大人の声をきく機会はあっても、当事者の子どもの立場で苦しみや困難が語られた文献、特に研究はほとんどありませんでした」と、研究・出版を思い立った背景を語る。欧米では、こうした子どもへの支援の必要性が認識され、研究や取り組みが進んでいる。田野中准教授は、とりわけ研究・実践の豊富さで際立っていたドイツに関心を持ち、2013年、現地調査に赴いた。そこで以前から着目していた原著の出版元を訪れ、翻訳の許諾を得ることになった。

精神疾患の親をもつ子どもが経験した困難・支えを調査
「イギリスやオーストラリアでは、子どもの5人に1人は親が精神疾患を患う経験をしているという報告もあります。日本でも全体数は明らかになっていないものの、その数は少なくないと推定されています」と田野中准教授。『ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書』(日本総合研究所、令和4年3月)によると、小学6年生、大学3年生を対象にした調査で小学生の15人に1人、大学生だと過去も含めて10人に1人がヤングケアラーの経験があることが分かっている。その内訳をみると大学生では母親を世話している人が35.4%と最も多く、その理由は精神疾患が多いという。
田野中准教授は、精神疾患を患う親をもった人を対象にインタビュー調査を行い、精神疾患の親をもつ子どもが直面する困難を明らかにしている。調査からわかったのが、子どもの大半が親の精神疾患について説明を受けておらず、「わけのわからないまま親の症状をみるしかない生活」を送っていたことだった。「親の症状による言動に巻き込まれ、時には夜中に家を飛び出した経験を話す人もいました」と田野中准教授。学童期から思春期にかけて見られたのが「世話をされない苦しい生活」だ。両親ともに子どもの世話ができず、学校の給食だけで食事をしのいだり、基本的な生活習慣を教えられないこともある。同級生との違いを感じ自己肯定観が低下する人も少なくないという。「精神疾患の親をもつ子ども全てが同様の困難を抱えるわけではありません。 しかし、いずれの年代でも自分の気持ちを誰からも受け止められず『親の言動に振り回される精神的不安定さ』『心を許せる友達や安心できる場所のない苦しさ』『我慢だけを強いられ、周囲からも支えられない苦しさ』が色濃く表れていました」。田野中准教授が強く感じたのは、子どもの困難が親の症状や家庭内の養育不足だけでなく、「家庭外」の理解不足や支援の少なさによってもたらされていることだった。
研究・取り組みが進むドイツの事例に学ぶ家族・子ども向け支援
田野中准教授は、精神疾患がある親をもつ子どもに対する支援が特に充実しているドイツの事例を調査・研究。その一つとして「CHIMPS(Children of mentally ill parents)プログラム」という支援プログラムについて報告している。
プログラムでは、親、子ども、そして家族と段階を踏んで専門スタッフが面談を行い、状況把握やそれぞれの気持ち、今後に対する思いなどを家族で共有する。「支援のポイントの一つは、家族のコミュニケーションを促すこと。二つ目には、スタッフが見守るなか、精神疾患の親自身が自らの疾患や症状を子どもに説明することです。さらに親、子ども双方が症状等に対する思いを話すことです。これらは、家庭に帰った時にスタッフがいなくても親子で気持ちや困りごとを話し合えるようにするために行われています。そして三つ目には、家族には必ず『自ら回復する力』があると信じ、それを引き出すことです」。特筆すべきは、精神疾患がある親だけでなく、子どもの声をしっかりきく時間をとっていることだ。そのため、子どもへの面談は、可能な限り親を同席させずに行われる。子どもの気持ちや困り事の把握を大切にするのと並行して、心理士が子どもの精神的健康状態の把握にも努めるという。それに加え、親の症状が悪化して養育役割を十分果たせなくなった時には、生活支援サービスなどの社会資源につなげられる仕組みもある。


「日本ではこうした家族向け、子ども向けの支援が圧倒的に不足しています」として田野中准教授は、子どもを含めた家族全体を継続的に支援できる体制の必要性を説く。「今後は、周囲の大人や地域社会の理解を促す取り組みに加え、精神疾患がある親をもった子どもの経験や支えとなっていることを今苦しんでいる子どもに共有してもらうため、子どもによる子どものための情報を伝えていきたい。そのための準備を進めているところです」と田野中准教授。まさに今、支援を必要としている子どもたちのために、力を尽くしている。
*精神疾患の親をもつ子ども達を支援する団体「CAMPs」のWebサイト「CAMPs ~あなたの大切な時間~(子どもによる子どもための情報)が公開になりました。田野中准教授は「CAMPs」の代表をつとめています。
https://camps-t.com/

BOOK/DVD
このテーマに興味を持った方へ、
関連する書籍・DVDを紹介します。
-
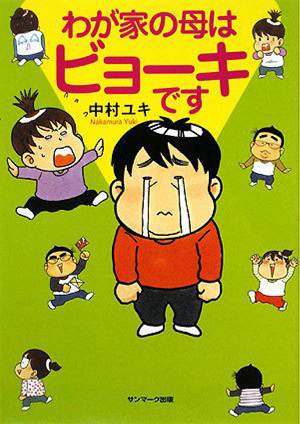
『わが家の母はビョーキです』中村ユキ/サンマーク出版
-

『レジリエンス こころの回復とはなにか』セルジュ・ティスロン 著、阿部又一郎 訳/白水社
-

『生きる冒険地図』プルスアルハ/学苑社
-
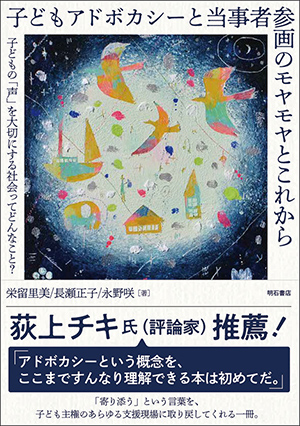
『子どもアドボカシーと当事者参画のモヤモヤとこれから-子どもの「声」を大切にする社会ってどんなこと?』栄留里美、長瀬正子、永野咲/明石書店
-

『ネグレクトされた子どもへの支援 理解と対応ハンドブック』安部計彦、加藤曜子、石井昭男/明石書店
教員著作紹介
-
『悲しいけど、青空の日 親がこころの病気になった子どもたちへ』サウザンブックス社(シュリン・ホーマーヤー 著、田野中恭子 訳)
-
『ケアの実践とは何か 現象学からの質的アプローチ』
-
『ケアの実践とは何か 現象学からの質的アプローチ』ナカニシヤ出版(分担執筆)
-
『統合失調症の看護ケア』中央法規出版株式会社(分担執筆)
表彰
-
第18回佛教大学学術賞 2021年10月
-
2020年度日本公衆衛生看護学会 学術奨励賞2020年12月
田野中 恭子/ 佛教大学 保健医療技術学部准教授
TANONAKA Kyoko
[職歴]
- 1992年4月~1997年3月 株式会社 ベネッセコーポレーション
- 2002年4月~2007年3月 医療法人西陣健康会 堀川病院・保健師
- 2007年4月~2010年3月 京都橘大学・看護学部・助手
- 2012年4月~2020年3月 佛教大学・保健医療技術学部・講師
- 2020年4月~現在に至る 佛教大学・保健医療技術学部・准教授

